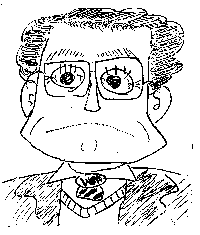Alumni Association
五劫会 (同窓会) 開催のお知らせ
2026年3月7日(土)、静岡市清水区にて五劫会(同窓会)を開催いたします。坂田先生、衛藤先生、渡邉先生にもご出席を賜る予定でございます。
卒業生の皆様には、メールや郵送にて順次ご案内を差し上げておりますが、コロナ禍を経てご連絡が取れない方もおられるかと存じます。詳細につきましては、下記までお問い合わせいただけますと幸いに存じます。
皆様にお目にかかれますことを心より楽しみにしております。
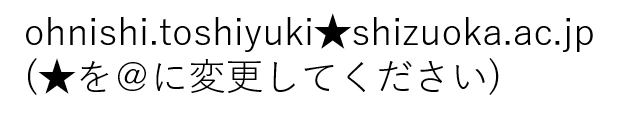
~静岡大学農学部 植物化学研究室~
静岡大学農学部は,昭和22年に静岡県立農林専門学校として発足し,静岡県立農科大学へ改名後 (昭和25年),昭和26年に静岡大学農学部となりました。発足当初,農学部は静岡県磐田市にキャンパスがありましたが,昭和48年に静岡県静岡市に位置する静岡キャンパスへ移転し,平成27年に新校舎に建て替えられました。静岡キャンパスは日本平につながる丘陵に位置しており,富士山と駿河湾を眺望できる絶好のロケーションにあります。農学部は,静岡キャンパスや地域フィールド科学教育研究センター藤枝フィールドに静岡の代表的な農作物である茶や柑橘,花卉などの栽培圃場を持ちます。共同利用施設であるグリーン科学技術研究所の分子構造解析部やゲノム機能解析部には大型質量分析装置や次世代シーケンサー,共焦点レーザー顕微鏡など生命現象を分子レベルで解析するために必要な分析機器が揃っていることから,静岡大学農学部では,フィールドからバイオテクノロジーに至る幅広い分野を通して研究や学生教育が活発に行われています。植物化学研究室は,農産製造学講座(研究室)に始まり,学科改組などに伴い天然物化学研究室,天然物有機化学研究室に改名し,現在に至っています。農産製造学講座では,農産物や海洋天然物に注目し,特にチャの化学的機能の解明を目指して,酒戸弥次郎先生 (名誉教授), 中林敏郎先生 (名誉教授),伊奈和夫先生 (名誉教授),坂田完三先生 (京都大学名誉教授),衛藤英男先生 (名誉教授),渡邉修治先生 (名誉教授) が研究を牽引されてきました。 現在は,轟泰司教授,大西利幸教授,竹内純准教授が一つの研究グループを構成し,学生20名以上とともに,植物ホルモンや二次代謝産物が制御する生命現象の解明にちなんだ独自のテーマに取り組んでいます。
~静岡大学農学部 五劫会~
五劫会は,静岡大学 農学部 農産製造学講座をルーツにする研究室の同窓会です。その名称は、真野三蔵氏 (昭和50年卒、 第20回生) によって命名されました。これは、 「じゅげむじゅげむ五劫のすりきれ・・・・・」から引用されたものです。四劫とは世界の成立から破滅に至る四大期で、世界が成立して人間が住み、 地獄から色界天までが成立する期間 (成劫)、人類が世界に安穏に存在する期間 (住劫) 、 世界が破滅するに至る期間 (壊劫)、次の世界が成立するまでの何もない期間 (空劫) をさします。
五劫会とは、四劫よりも長く永遠にこの会が続くという願いが込められています。
~出典元 農産製造学講座43年を顧みて 静岡大学五劫会 (旧農産製造学講座)~
~2019年 五劫会~


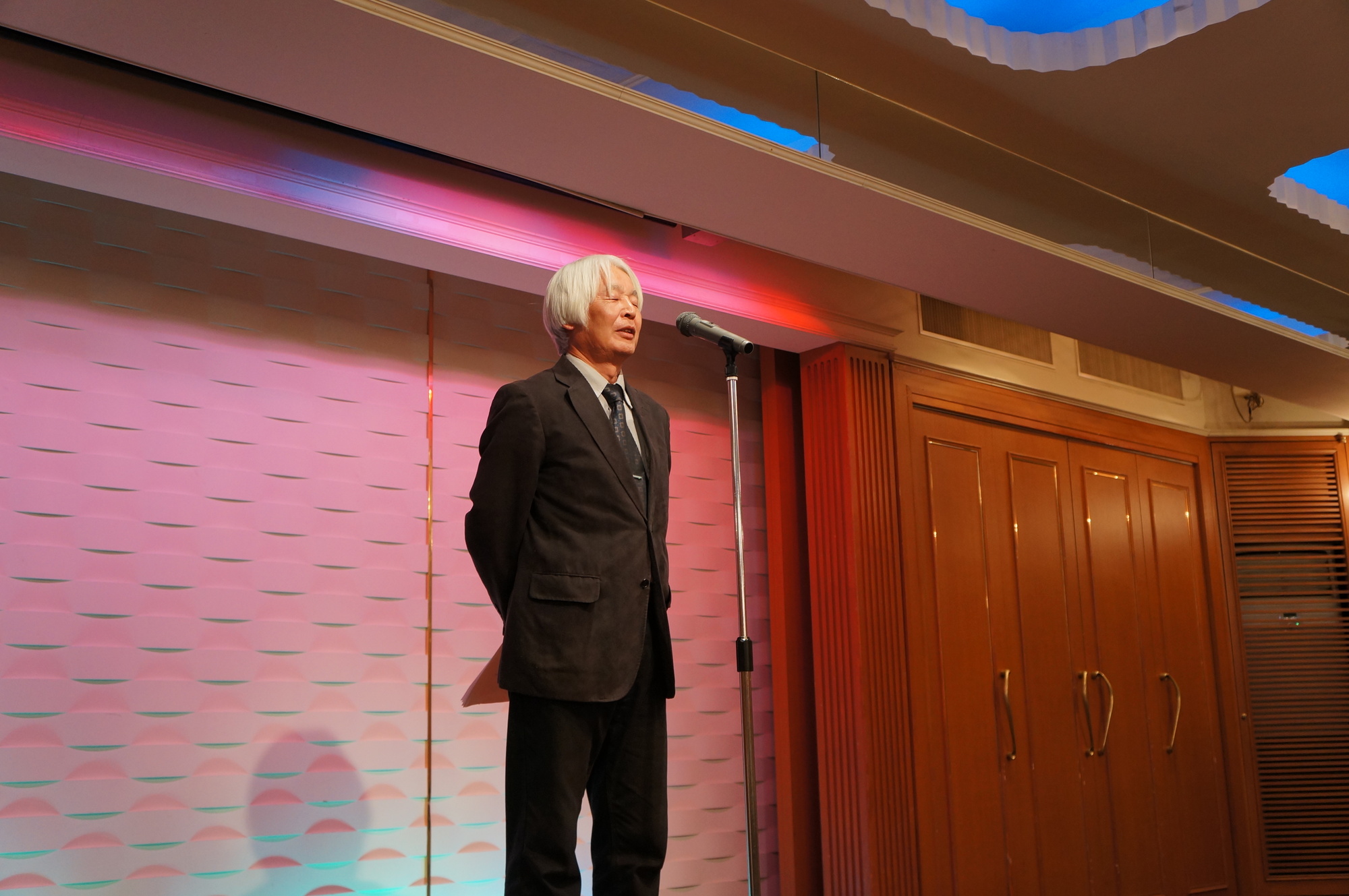
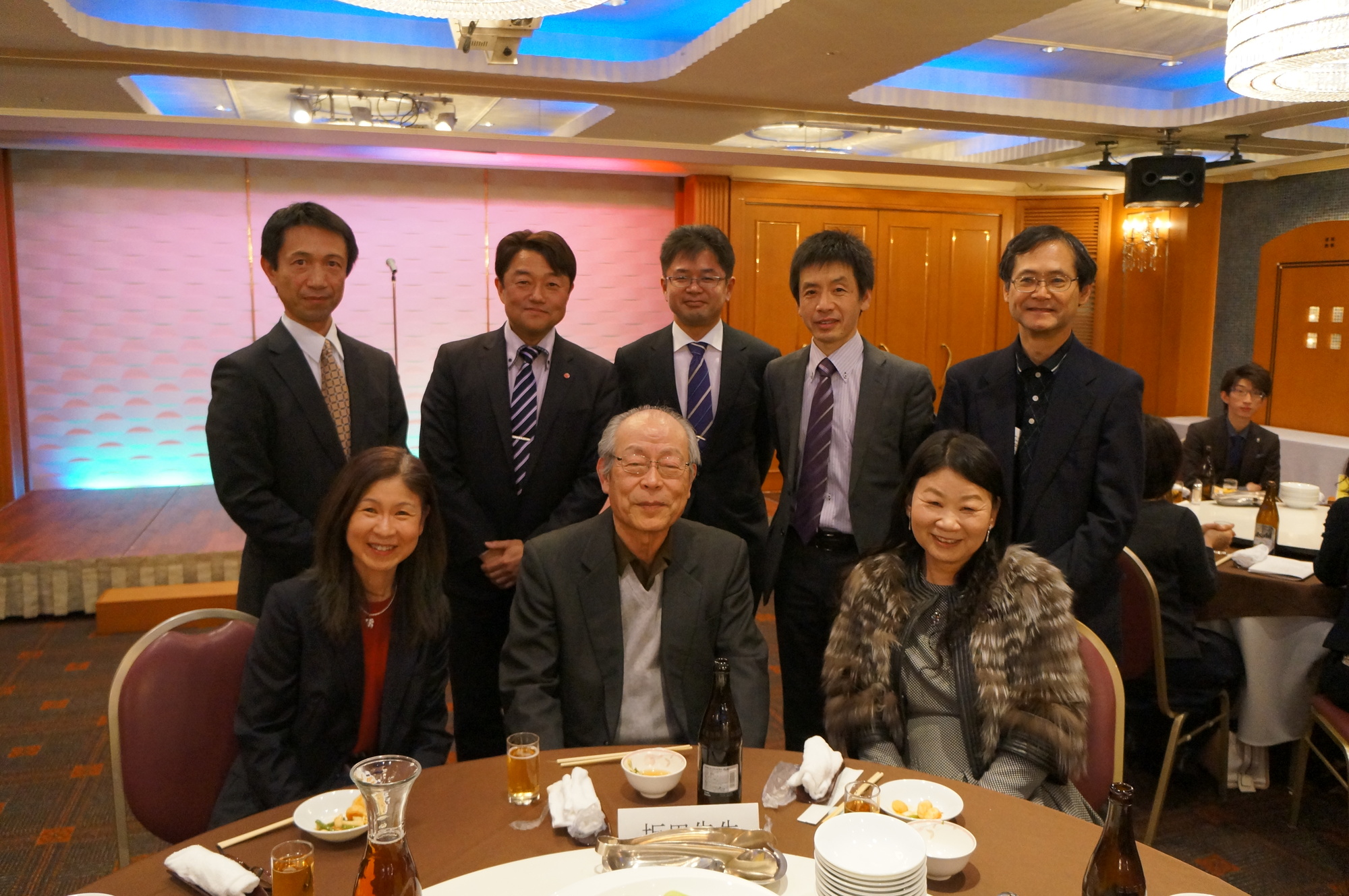




~2016年 五劫会~

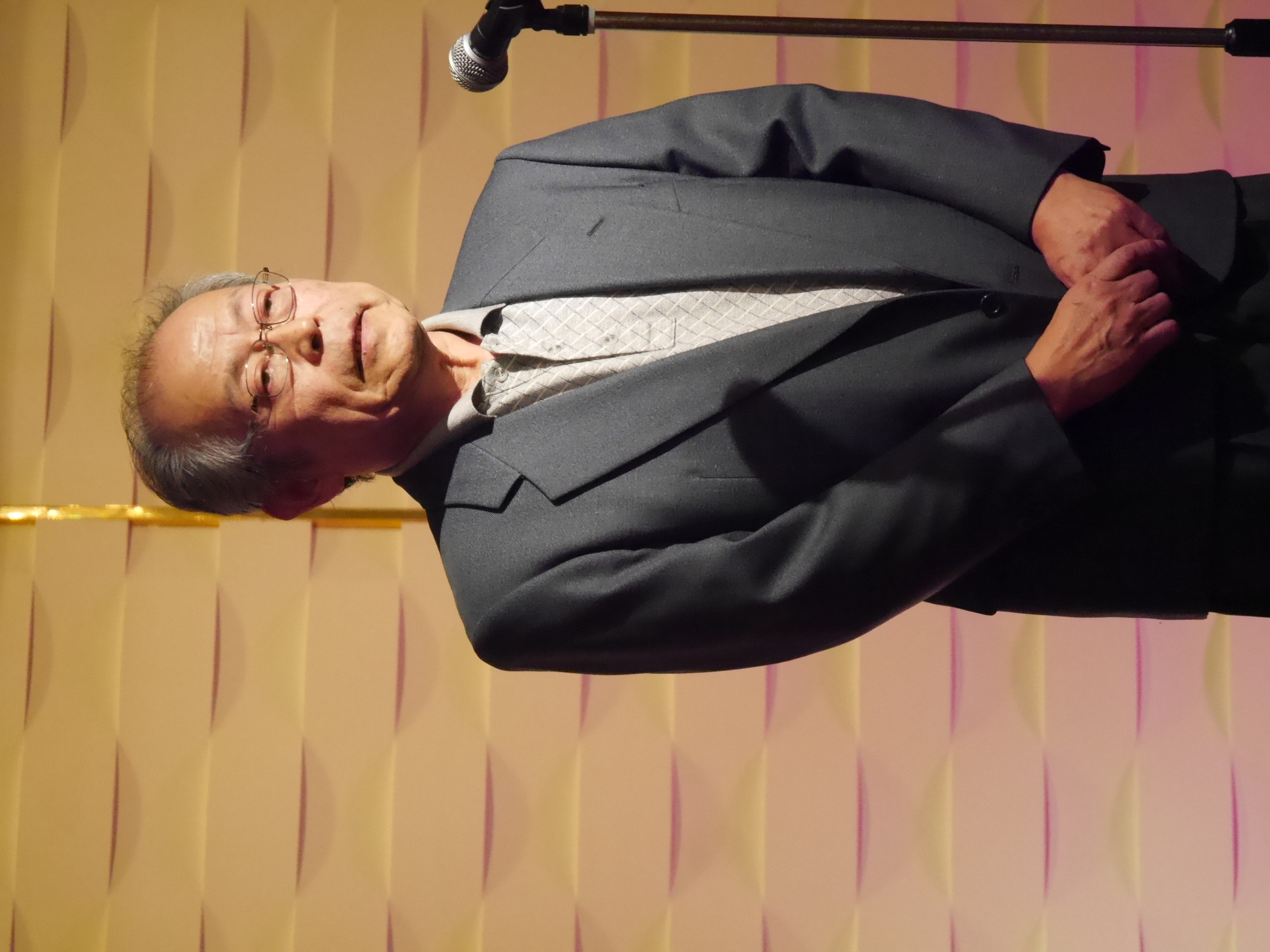








農産製造学講座43年を顧みて (静岡大学五劫会 (旧農産製造学講座) 1995年発刊) より抜粋
はじめに
全国の大学に押し寄せた大学改革の波は我が静岡大学農学部も決して例外ではなく、平成元年4月から静岡大学農学部は従来の5学科から3学科体制へと改革が進められました。卒業生諸氏には本当に懐かしい“農芸化学科”の名称もこれと同時に過去のものになりました。また、昭和27年から43年間続いた長い歴史と数々の伝統を持つ“農産製造学講座”の名称も平成6年3月末日、第23回の大学院修士課程の学生の修了と共に消えようとしています。平成6年4月からは、新生、応用生物化学科(教官は生物資源化学および生物制御化学講座所属)の中で教育・研究が進められることになりました。
組織、名称は変わっても学内における研究室の場所、スタッフは変わりありません。新学科の中でも食品製造、天然物化学グループとして、農産製造学講座に脈々と流れていた伝統を受け継ぎ、新しい伝統を作り上げるための努力も重ねています。
幸い、過日の農産製造学講座同窓会総会の席において、今後は同窓会名称も“五劫会”と改め、新、旧の同窓生が一体となって長い歴史と数々の伝統を守ると共に新しい伝統をも築き上げるよう承認されました。
半世紀に亘る長い歴史に一応のピリオドが打たれることを期に“農産製造学講座43年を顧みて”と題した記念誌の発行を思い立ったものであります。
新、旧職員を交じえ、想いだされるままに文を綴って頂き、青春時代の思い出として頂きたく小冊子の作成を企画しました。
また文末には農産製造学講座の研究の流れも御披露申し上げました。
平成6年3月
伊 奈 和 夫
あとがき
昭和22年の静岡農専に始まった農産製造学研究室は昭和26年の学制改革により、県立静岡農科大学となり、さらに国への移管により、静岡大学農学部となって、六所先生が担当されて初めて、大学昇格後の農産製造学の歴史が始まることが、神谷先生の「「農芸化学科創設時の思い出」に紹介されていますが、この伝統ある名称も本学部から消えることとなり、卒業生諸氏にとっても大きな時代の流れを感じておられることと思います。
昭和56年10月に赴任した時、約25年前大学紛争で1年間の大学封鎖という異常な経験をし、大学が荒れ放題に荒れたのを目の当たりにしたことのある私は、壁にも落書き一つない余りにきれいな農学部の建物に驚いたことが懐しく思い出されます。
大学における講座制度はそれまでの大学の封建性などの諸悪の根源とされ、大学紛争時のスローガンの一つでありました「講座制解体」は、あれほどの犠牲を払っても実現しなかったのですが、近年の農学系学部での改組に伴う旧講座制からの大講座制への速やかな移行には隔世の感があります。アメリカの制度のつまみ食いに過ぎない現行の大講座制も、文部省にとっては大学の管理運営に都合がよく魅力的なものと写ったようで、数年前から始まった農学部の改組では、ほとんどの大学で大講座制が導入されました。これに伴い、上述の長い伝統のある農産製造学講座も本年度の修士課程の学生諸君の卒業をもってなくなってしまうこととなったわけです。卒業生諸氏にとっては、農産製造学講座を「故郷」のような親しみをもって感じておられたことと思われ、この会の名称の募集の際に応募してくださった名称の中に「農産製造学」のいずれかの文字が入ったものが多かったことからも推測されます。しかしながら、これからの卒業生にとっては、農産製造学講座は過去の遺物となるわけです。とはいえ、今でも、農産製造学講座がカバーしてきた有機化学を基礎として生物が示す生命現象に関わる事象および人類の生存に必須の食品を科学する学問分野は、技術の進歩とともに少しずつ形を変えながらもますます重要なものとなりつつあります。「農産製造学講座」という名称はなくなりますが、この教育研究分野は、一つの研究グループとして存続してゆくことになっております。同じ学科に学び、同じ研究グループの一員としてセミナーや卒論研究を通じて培われた先輩と後輩、同級生、教官との間の絆はそれぞれの卒業生にとって心強く、頼りになるものであることは、西洋においても「Old Boy’s Network」というものがあることからもわかります。
こうして新しい体制から生まれてくる卒業生達も含めた会に、過日の同窓会で「五劫会」という素晴らしい名前が付けられました。「永遠に発展し続ける会」とは、各分野でますますご活躍の皆様方の会にまことに相応しい名称であり、一層のご活躍を祈念するものといえます。この会を通じての諸先輩の方々と新しい会員および大学の教官との交流が、色々な意味で活用され、この会の名称「五劫会」のように皆様のますますの発展を願って「あとがき」といたします。
静岡大学農学部付属魚類餌料実験実習施設
坂田 完三